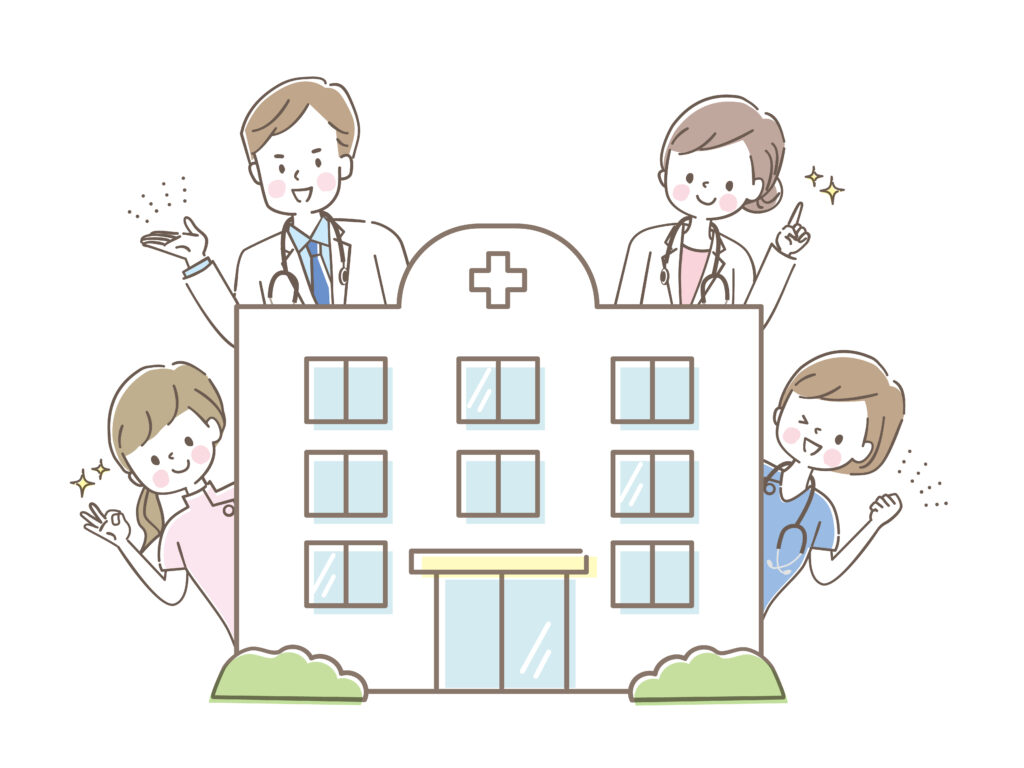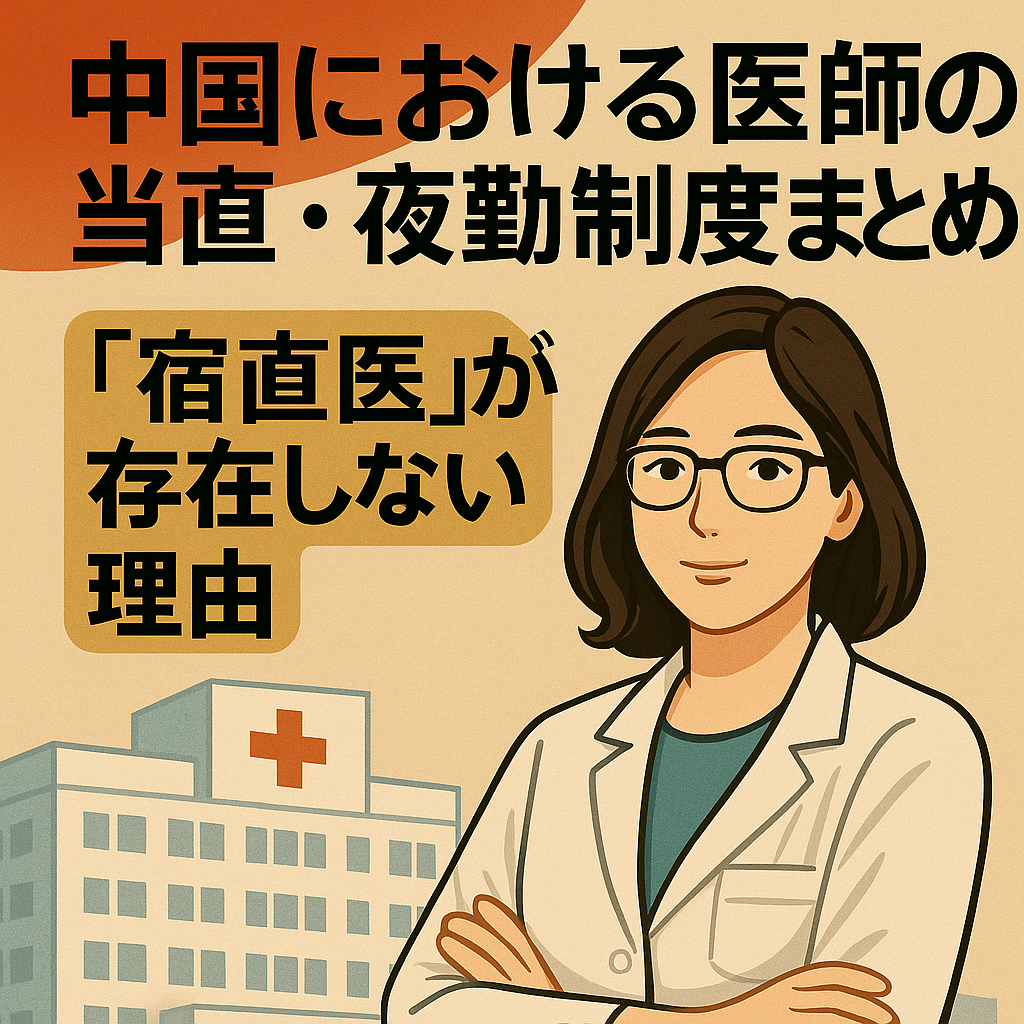なぜ「医療=サービス業」と語られるのか
先生方は日々の診療現場で、「自分の仕事はサービス業なのか?」と感じたことはありませんか?
患者への説明の仕方ひとつで信頼関係が大きく変わることを、現場で実感されていると思います。その一方で、私たち医師は生命を預かる存在であり、単なる接客業とは明らかに異なる特別な責任を負っています。
本記事では、「医療=サービス業」としての側面と、それを超える医療特有の性質を整理し、日常診療にどう活かせるのかを考えていきます。
医療サービスが持つ「サービス業」としての共通点
「医療にサービス業の要素がある」と言われると、どこか違和感を覚える先生も多いのではないでしょうか。
しかし、医療行為を患者にとっての”体験”として捉えると、一般のサービス業と驚くほど共通点があります。ここでは、その共通点を改めて確認してみましょう。
1. 無形性(Intangibility)
医療サービスは形のない価値を提供します。治療や診断は「商品」として手に取ることができず、患者にとっては不確実性を伴う体験です。
2. 同時性(Inseparability)
診療行為は、提供と消費が同時に発生します。診察・検査・処置の現場で、患者の体験そのものが医療の成果に直結するのです。
3. 異質性(Heterogeneity)
医師・看護師・スタッフによって対応や判断が異なり、それが患者の印象や満足度に大きな影響を与えます。
4. 消滅性(Perishability)
診療の「空き枠」は在庫化できず、機会を逃せば消えてしまいます。医療資源の効率的な運用が常に求められます。
5. 患者との共同生産(Co-production)
患者の生活習慣改善や治療アドヒアランスは、医療成果に不可欠です。患者との協働が、治療の質を左右します。
医療が一般のサービス業と異なる「固有の特性」
一方で、「医療はサービス業では語り尽くせない」という実感も強いはずです。
私たちはただ”満足”を提供するだけではなく、患者の生命・健康という代替不可能な価値を守っています。ここでは、医療特有の性質を整理していきます。
1. 情報の非対称性
医師は圧倒的な専門知識を有する一方、患者は自ら判断することが困難です。このため、インフォームド・コンセントや丁寧な情報開示が不可欠となります。
2. 需要の予測困難性
発症や急変は予測できず、必要な医療量を事前に確定することはできません。救急医療や病床数の調整が典型例です。
3. 公共性と外部性
予防接種や感染症対策は、社会全体の利益に直結します。医療は個人向けサービスであると同時に、「公共財」としての性格を持ちます。
4. 安全性・品質確保の重要性
医療ミスは人命に関わるため、他のサービス業よりもはるかに厳格な安全管理が求められます。
5. 制度・規制依存性
診療報酬制度、医療法、保険制度といった法的枠組みに強く制約されており、市場原理だけでは最適化できない構造になっています。
6. 契約関係の三者性
患者、医療機関、保険者の三者で成立する契約構造は、他のサービス産業には見られない大きな特徴です。
医師・医療機関にとっての実務的インプリケーション
「では、こうした特性を踏まえて、私たちは日常診療や経営でどう活かすべきか?」
理論だけでは現場は変わりません。ここからは、医師・医療機関が明日から実践できる具体的な視点を見ていきましょう。
1. 患者体験の質(Patient Experience)を高める
なぜ重要なのか
サービス業の視点を取り入れることで、説明・接遇・待ち時間管理などが改善され、患者満足度とリピート受診、さらには口コミによる新患獲得につながります。
具体的な実践例
【診察室での工夫】
- 視線の高さを合わせる:患者と目線を同じ高さにして話すことで、心理的距離が縮まります
- 専門用語を避ける:「浮腫」→「むくみ」、「投薬」→「お薬」など、患者目線の言葉選びを意識
- 3つのポイントで説明:情報過多を避け、「今日の診断」「治療方針」「次回までにすること」の3点に絞る
【待ち時間対策】
- 予約システムの導入で待ち時間の見える化
- 待合室に現在の待ち人数を表示
- 待ち時間が長引く場合の声かけルール設定
【スタッフ教育】
- 受付・看護師への接遇研修の定期実施
- 患者アンケートのフィードバック共有
- 好事例の院内表彰制度
注意点
患者満足だけを追求すると、過剰な検査や不必要な処方につながるリスクがあります。医学的妥当性とのバランスを常に意識しましょう。
2. 制度・報酬設計を理解する
なぜ重要なのか
診療報酬制度や保険制度を理解していないと、経営的に持続不可能な診療スタイルに陥ったり、算定漏れで収益を失ったりするリスクがあります。
具体的な実践例
【診療報酬の理解を深める】
- 診療報酬改定のポイントを年2回確認(4月・10月)
- 自院でよく使う加算項目の算定要件を明文化
- レセプトチェック体制の強化で返戻・査定を防ぐ
【制度を活用した経営改善】
- 地域包括ケア病棟、在宅医療など制度上評価される領域への参入検討
- 施設基準の取得可能性を定期的に見直し
- DPC/PDPSデータを分析し、診療の効率化ポイントを特定
【医療政策への関心】
- 医師会や学会の政策提言に目を通す
- 地域医療構想や医師偏在対策など、中長期的な制度変化を把握
注意点
制度に過度に依存すると、改定時の影響を大きく受けます。複数の収益源を持つ経営の多角化も視野に入れましょう。
3. チーム医療と組織マネジメント
なぜ重要なのか
医療の「異質性」を減らし、誰が担当しても一定の質を保つには、チーム全体での標準化とスタッフのエンパワーメントが不可欠です。
具体的な実践例
【標準化の推進】
- クリニカルパスやプロトコルの作成・運用
- 電子カルテのテンプレート機能を活用した記載の統一
- 定期的なカンファレンスで治療方針の共有
【タスクシフト/タスクシェア】
- 特定行為研修修了看護師の活用
- 医師事務作業補助者(医療クラーク)への書類作成委譲
- 薬剤師による薬歴管理・服薬指導の充実
【心理的安全性の確保】
- 失敗を責めず学びに変える文化づくり
- 月1回の全体ミーティングでスタッフの声を吸い上げ
- インシデント報告を評価し、改善に活かす仕組み
【リーダーシップ開発】
- 医師以外のスタッフにも小さな権限委譲
- 看護師長・事務長などのマネジメント研修参加支援
- 後輩医師の教育・指導スキル向上プログラム
注意点
標準化しすぎると、個々の患者に合わせた柔軟な対応が失われます。「標準」と「個別化」のバランスを意識しましょう。
4. 情報公開と信頼構築
なぜ重要なのか
情報の非対称性を補い、患者が納得して治療を受けられる環境をつくることが、長期的な信頼関係とアドヒアランス向上につながります。
具体的な実践例
【院内での情報提供】
- 診療実績・手術件数・合併症率などのデータ公開
- 待合室での健康教育資材の設置(ポスター・パンフレット)
- 患者向け勉強会・健康講座の定期開催
【オンラインでの情報発信】
- クリニック/病院のウェブサイトでの医師紹介・診療方針の明示
- ブログやSNSでの健康情報発信(注意:広告規制の遵守)
- Googleマイビジネスなどの口コミへの丁寧な返信
【エビデンスに基づいた説明】
- ガイドラインや論文を患者向けに翻訳して説明
- 治療選択肢を複数提示し、それぞれのメリット・デメリットを明示
- セカンドオピニオンの受診を推奨する姿勢
【患者の声を聴く仕組み】
- 定期的な患者満足度調査の実施
- 匿名の意見箱設置と、寄せられた意見への対応公表
- 患者参加型の医療安全委員会の設置
注意点
情報公開は諸刃の剣です。誤解を招く表現や過度な期待を与える宣伝は医療法・医療広告ガイドラインに抵触する可能性があります。弁護士や専門家の確認を経ることをお勧めします。
5. データ活用による継続的改善
なぜ重要なのか
現代の医療経営では、EBHM(Evidence-Based Healthcare Management)の考え方が重要です。勘や経験だけでなく、データに基づいた意思決定が求められます。
具体的な実践例
【診療データの可視化】
- 患者数・疾患別内訳・平均在院日数などのKPI設定
- 月次でのダッシュボード作成と経営会議での共有
- DPCデータやレセプトデータの分析による収益構造の把握
【質指標(QI)のモニタリング】
- 再入院率・術後感染率・転倒転落発生率などの追跡
- ベンチマークとなる他院や全国平均との比較
- 改善活動のPDCAサイクルを回す
【患者フィードバックの定量化】
- NPS(Net Promoter Score)などの指標導入
- 患者満足度と診療成果の相関分析
- クレーム内容の分類と傾向分析
注意点
データ分析に時間を取られすぎて、本来の診療がおろそかになっては本末転倒です。効率的なデータ収集の仕組みと、分析を担う専門スタッフの配置を検討しましょう。
6. 持続可能な働き方の実現
なぜ重要なのか
医師の働き方改革が進む中、長時間労働に依存した医療提供体制は限界を迎えています。スタッフのwell-beingが、結果的に患者ケアの質を高めます。
具体的な実践例
【労働時間管理】
- 勤怠管理システムの導入と残業時間の可視化
- 当直明けの休息確保(インターバル規制)
- 複数主治医制・主治医グループ制の導入
【業務効率化】
- 音声入力やAI問診の活用
- オンライン診療の導入で通院負担軽減
- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による事務作業自動化
【ワークライフバランス】
- 有給休暇取得の推奨と計画的な人員配置
- 育児・介護中のスタッフへの柔軟な勤務体制
- メンタルヘルス相談窓口の設置
注意点
働き方改革は「医師の負担を減らす」だけでなく、「患者ケアの質を維持・向上させながら実現する」ことが重要です。単なる労働時間削減だけでは、患者満足度が下がるリスクがあります。
まとめ:医療は「サービス業」かつ「公共財」
最後に、もう一度「医療はサービス業か?」という問いに立ち返ってみましょう。
答えは「イエスでもあり、ノーでもある」です。
医療はサービス業の特性を持ちながらも、公共性・安全性・制度依存性という他の産業にはない性格を兼ね備えています。
私たち医師がこの二重性を理解し、以下の6つの視点を日常診療・経営に取り入れることが、これからの医療キャリアや医療経営の成功に直結していくのです。
- 患者体験の質を高める
- 制度・報酬設計を理解する
- チーム医療と組織マネジメント
- 情報公開と信頼構築
- データ活用による継続的改善
- 持続可能な働き方の実現
それぞれの取り組みは、単独で行うのではなく、相互に関連し合いながら医療の質を高めていくものです。まずは自院でできることから、一歩ずつ始めてみましょう。
監修
鎌形博展 株式会社EN 代表取締役兼CEO、医療法人社団季邦会 理事長
専門科目 救急・地域医療
所属・資格
- 日本救急医学会
- 日本災害医学会所属
- 社会医学系専門医指導医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 国際緊急援助隊・日本災害医学会コーディネーションサポートチーム
- ICLSプロバイダー(救命救急対応)
- ABLSプロバイダー(熱傷初期対応)
- Emergo Train System シニアインストラクター(災害医療訓練企画・運営)
- FCCSプロバイダー(集中治療対応)
- MCLSプロバイダー(多数傷病者対応)
メディア出演
- フジテレビ 『イット』『めざまし8』
- 共同通信
- メディカルジャパン など多数
SNSメディア
- Youtube Dr.鎌形の正しい医療ナビ https://www.youtube.com/@Dr.kamagata
- X(twitter) https://x.com/Hiro_MD_MBA
関連リンク
- 株式会社EN https://www.med-pro.jp/en/
- 医療法人社団季邦会 https://wellness.or.jp/kihokai/