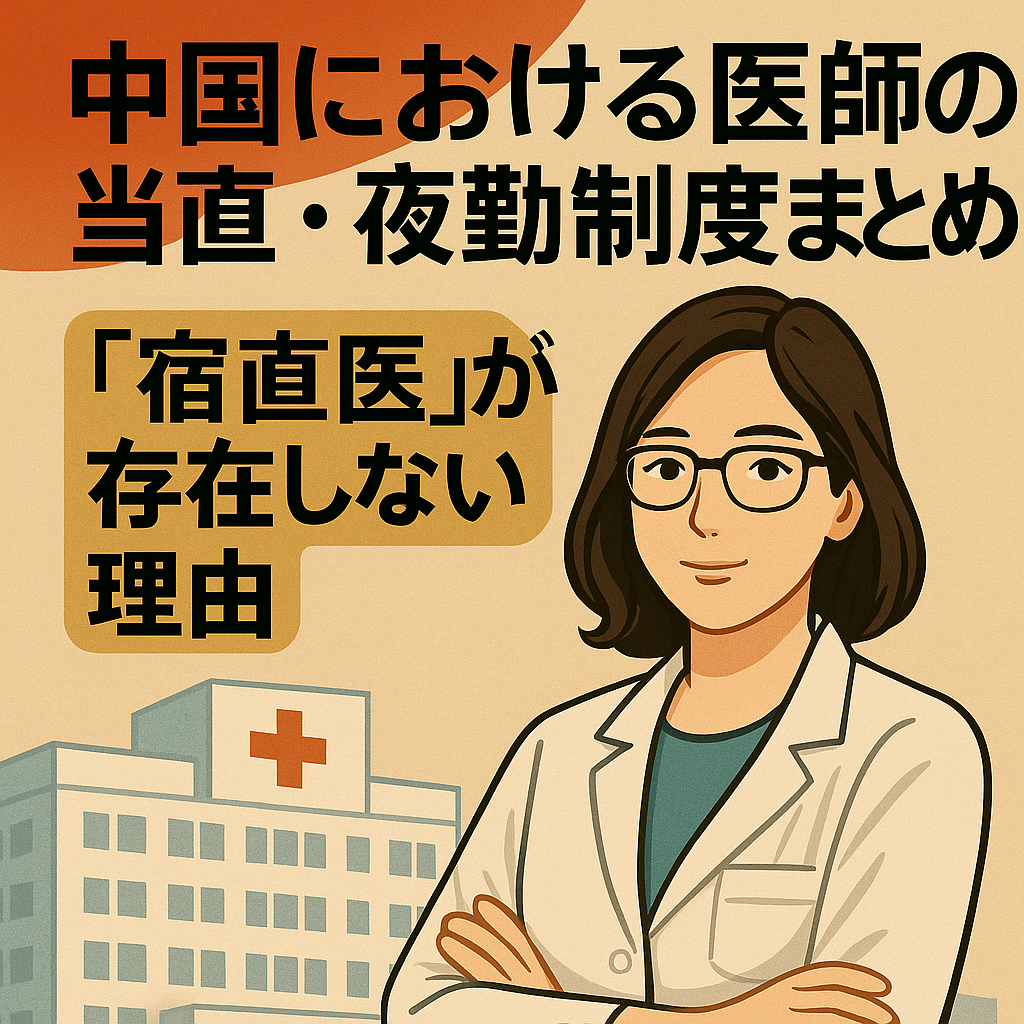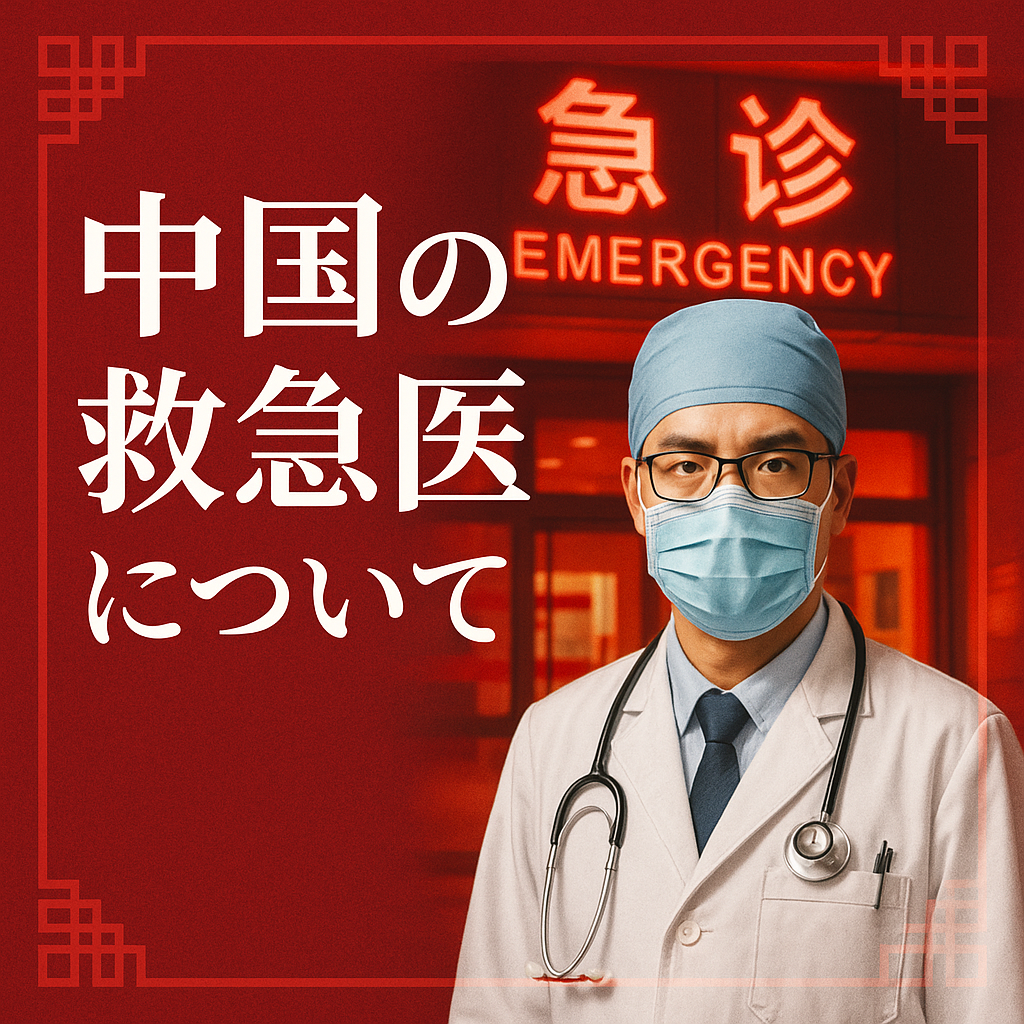上海の病院に導入された多関節型手術支援ロボット「ダビンチ」。外科医がコンソールに座ってロボットアームを操作し、患者に低侵襲手術を施す(新華社)
急成長する中国の手術ロボット市場
中国の手術支援ロボット市場は近年急速に拡大しています。市場調査会社フロスト&サリバンのデータによれば、2020年時点で約4億3,000万ドル(約680億円)だった市場規模が、2026年には38億4,000万ドル(約6,100億円)に達する見通しです。特に腹腔鏡下手術向けロボット(いわゆるダヴィンチ型ロボット)が中国市場の中心で、2026年にはその分野だけで23億2,000万ドル(約3,700億円)規模に拡大すると予測されています 。これは年平均で40%以上という驚異的な成長率であり、中国政府の後押しや技術革新を背景に市場が飛躍しつつあることを示しています。 こうした成長の裏付けとして、米国直観外科手術社(インテュイティブ・サージカル)が開発した「ダビンチ」ロボットの中国での普及も加速しています。ダビンチは2006年に中国で最初に導入されて以来、中国全土の300余りの病院に400台以上が設置され、累計で54万人超の患者がこのロボットによる手術を受けました 。もっとも、これは依然として中国全体の手術件数から見ればわずか数%程度であり、将来的な普及余地は大きいと言えます。実際、世界全体で見てもロボット支援手術は現状で全外科手術の約2.8%に過ぎませんが、2030年には14%に達するとの予測もあります 。中国は今後10年間でロボット手術が急成長する次のフロンティアになるとの見方もあり 、各方面から大きな注目を集めています。
国産ロボット企業の台頭と主要製品
中国の新興企業コーナーストーン・ロボティクス(康诺思腾)が開発した腹腔鏡手術ロボット(2024年、サウジアラビア・リヤドの技術展示会にて)(SCMPより) 近年、中国では国産の手術支援ロボットを開発する企業が次々と登場し、市場における存在感を高めています。代表的な企業とその主な製品・特徴を以下に挙げます。
微創机器人(MicroPort MedBot)
上海に拠点を置く中国トップクラスの手術ロボット企業です。腹腔鏡下手術用の多関節ロボット「図邁(Toumai)」をはじめ、骨科手術ロボット「鸿鹄(Honghu)」、経気管支ロボットや経皮的手術ロボットなど5つの主要分野を網羅する製品ラインを揃えています。2023年には図邁を用いた世界初の5G遠隔手術100例達成を公表し、遠隔医療への応用でも話題を集めました 。
北京天智航(Tinavi)
整形外科手術ロボットのパイオニアで、2005年創業の老舗企業です。主力製品「天璣(Tianji)」は骨折手術や脊椎手術のナビゲーション・定位を支援するロボットで、精度0.8mmという極めて高い位置決め精度を実現しています 。四肢や骨盤、頸椎・胸椎・腰椎・仙骨まで全ての脊柱セグメントの手術に対応できる世界唯一のロボットと評価され 、術中のX線被曝を70%以上低減し手術効率も20%以上向上させることが報告されています 。2016年に中国初の国産手術ロボットとして認可を取得し、以降全国300以上の病院に導入、2024年第1四半期までの累計手術件数は7万件を超えました 。特に2019年にすでに天璣ロボットによる5G遠隔手術も9件実施され、いずれも成功しています。
精鋒医疗(Edge Medical Robotics)
深圳市に本拠を置くスタートアップで、2017年設立という新興企業ながら大手VCからの出資を受け急成長しています 。単孔式と多孔式の両方の内視鏡手術ロボット技術を有する点が特徴で、これは世界でも米国企業を除けば初めての快挙です 。同社の多関節ロボット「MP1000」は4本アームを備え、主要な性能指標で「ダヴィンチ」の標準モデルに劣らないことが臨床試験で示されたといいます。2023年8月にはMP1000が中国国家薬監局(NMPA)から承認を取得し、国内製として初めて泌尿器科・婦人科・一般外科・胸部外科の「全科目」に対応可能な腹腔鏡ロボットとなりました。また単一の小さな切開孔から手術器具を挿入する単孔式ロボット(SP1000)も開発しており、将来的には自然腔(経口や経肛門など)からの手術も視野に入れています。
哈尔滨思哲睿(Harbin Sagebot)
ハルビン工業大学発のベンチャーで、製品名「康多(KangDuo)」の腹腔鏡手術ロボットを提供しています。2018年には康多ロボットを使った世界初の5G遠隔腹腔鏡手術(動物実験)に成功し、技術力を示しました。康多は3本アームの開腹型コンソールを特徴とし、泌尿器科・婦人科・胸部外科・一般外科などで多目的に利用できます。2024年9月にはNMPAから国内承認を取得し、市場投入が始まっています。思哲睿は国内第1号のユニコーン企業にも選ばれており、単孔式や耳鼻科・脊椎内視鏡ロボットなど多彩なラインアップを開発中です。
その他の企業・分野
上記以外にも、中国では多領域に特化した手術ロボットが登場しています。例えば、威高集団(Weigao)は既存の医療機器大手ですが近年ロボット事業に参入し、骨科手術ロボット「妙手S」の開発や、脳神経・耳鼻科・脊椎向けの磁気ナビゲーション型手術ロボットにも取り組んでいます。また、柏惠维康(北京、Bohui Weikang)は神経外科手術ロボット「睿米(Remebot)」を開発し、国内で初めて脳外科手術ロボットの認可を取得しました。同社の製品はすでに全国300以上の医療機関に導入され、累計3万件を超える脳手術や歯科手術に使用されています。さらに、心血管領域では蘇州润迈德(RunMed)が血管内手術ロボットの開発で成果を上げており、冠動脈インターベンションをロボットで支援するシステムを世界に先駆けて実用化しつつあります。 このように、中国では腹腔鏡手術ロボットを中心に、骨科、脳神経、血管内治療、歯科まで多岐にわたる分野で手術ロボット企業が群雄割拠しています。その数は決して多くありませんが、ここ数年で一気に製品開発と商業化が進み、2022年以降だけで約10種類以上の国産手術ロボットが承認を取得したとも報じられています 。各社とも自社技術の強みを生かした特色あるロボットで、国内市場での採用を競い合っています。
技術性能と価格競争:ダヴィンチとの差は?
中国発の手術ロボット各種は、性能面でも海外製品に迫るレベルに達しつつあります。例えば前述の精鋒医疗(Edge)の多関節ロボットは、臨床試験において米インテュイティブ社の「ダヴィンチSi」システムに引けを取らない精度と操作性を示しました。微創機器人(MicroPort)の図邁ロボットも、前立腺がん根治術や腎部分切除術、肺がん手術など複数の高難度手術で国産ロボット初の成功例を打ち立て 、その有用性が実証されつつあります。また天智航の天璣ロボットは前述の通り0.8mm精度でナビゲーションを実現し、人間の手では困難なレベルの正確さでスクリュー挿入などが行えるといいます。
さらにAI(人工知能)技術や高性能な画像処理の活用も各社が工夫する点です。たとえば最新の手術ロボットは、手術部位の画像をリアルタイムで解析し、術中に病変部の識別や手術効果の評価まで自動でサポートできるようになりつつあります 。熟練医師の「透視眼」と「精密な手」を再現するような補助を提供し、術者の技量を底上げすることが期待されています 。中国企業でも手術映像のAI分析やロボットアームの自動制御に関する研究開発が活発で、例えば思哲睿(Sagebot)はAIを組み合わせた「自動縫合ロボット」の試作も発表しています(人間の介入なしで縫合を行う技術)。こうした要素技術はまだ研究段階ですが、将来的には”半自律的”な手術ロボットへ発展しうると考えられます。
一方で、価格面は国産ロボットが海外製に対抗する大きな武器です。米国のダヴィンチ手術ロボットは1台あたり約2,300万元(約4億6千万円)と非常に高額で、メンテナンス費用や専用器具のランニングコストも年間数百万円規模に上ります 。それに対し、中国製の腹腔鏡手術ロボットは平均で1台1,400万~1,700万元(約2億8千万~3億4千万円)程度と、ダヴィンチの価格の6~7割程度に設定されています 。企業間の競争激化により一部では更なる値下げも起きており、例えばハルビン思哲睿社は政府調達入札で538万元(約1億1千万円)という破格の安値でロボットを納入した例もあります 。また微創機器人の図邁ロボットも、2025年の入札案件で約1,199万元(約2億4千万円)というダヴィンチの半額近い価格で契約されました 。こうした価格競争は、「国産ロボットでコストを抑え、多くの病院に普及させよう」という中国政府の方針とも合致しており、市場拡大の一因になっています 。
もっとも、価格を下げれば必ずしも市場シェアが劇的に伸びるわけではありません。医療機関にとって最優先されるのは手術ロボットの性能と信頼性であり、多少高価でも実績のあるシステムを選ぶ傾向があります 。実際、2024年に中国国内で新たに導入された腹腔鏡手術ロボット台数を見ると、ダヴィンチが58台でトップ、対して平均価格1,000万元以下の国産ロボット全体では33台程度に留まっています 。また骨科ロボット市場でも、天智航の天璣ロボットは他社製品より価格が19%高いにもかかわらず50%のシェアを占めています 。このことは、単なる低価格だけではなく、製品の性能やアフターサービス、ブランド信頼性が病院の採用判断を左右することを示しています。国産メーカー各社は価格競争だけでなく、臨床現場での実績づくりや医師への教育支援などソフト面でも差別化を図る必要があるでしょう。
海外企業との競争力の比較
手術用ロボットの分野では、長らく米インテュイティブ・サージカル社の「ダヴィンチ」が世界市場を独占してきました。ダヴィンチは2000年に米FDA承認を取得した世界初の実用的な手術ロボットで、現在も世界シェア80%以上を維持する圧倒的トップ製品です 。一方、日本や欧州でも新たな競合機が生まれつつあり、日本では川崎重工業とシスメックスの合弁による「hinotori(ヒノトリ)」ロボットが2020年に国産第1号として承認されました。英米ではメドトロニック社の「Hugo」やジョンソン・エンド・ジョンソン社の「Ottava(オッターヴァ)」、英CMRサージカル社の「Versius(バーシアス)」など、多国籍企業が次世代システムを開発中です。こうした海外勢と比べた際の、中国国産ロボットの競争力について考察します。
市場シェアと導入実績
上述のようにグローバルでは依然ダヴィンチの独壇場ですが、中国国内に限れば状況は変わりつつあります。2025年初めまでの政府調達データによれば、中国での腹腔鏡ロボット新規導入台数はダヴィンチ12台に対し、精鋒医療 6台、微創社製1台、術锐(北京術鋭技術)社製1台と国産機が計8台を占めるまでになりました 。特に地方の中核都市や郊外の病院では国産ロボットが選ばれるケースが増えています 。低コストゆえ予算の限られた病院でも導入しやすいためで、実際に県レベルの病院市場は微創や精鋒、術锐、康多(思哲睿)といった国産ブランドがほぼ独占しつつあります。もっとも、中国の一流病院(主要都市の三甲医院)では依然としてダヴィンチの信頼性が評価される傾向が強く、こうした大病院では海外製と国産が棲み分け的に使われているのが現状です。
性能・技術面
操作性・精度に関して、国産ロボットは急速にキャッチアップしています。多くの中国製品が4本のロボットアームや3次元HD内視鏡といったダヴィンチ同等のハード構成を持ち、前立腺や腎臓、肺など臓器別の標準手術手順(術式)も整備され始めました。一部製品ではモジュール式のアーム設計(必要な本数だけ装着可能)や、単一の小切開で多器官にアクセスするデザインなど、独自の工夫でダヴィンチの弱点を補う動きもあります 。例えば瑞龍外科(Ronovo Surgical)という中国ベンチャーは、アームを1本ずつ独立可動できるモジュール型ロボットを開発し、狭い手術室でも設置しやすく複数手術室で効率的に使い回せるようにしました 。さらに日本や欧米の競合がまだ実現していない遠隔手術の分野では、中国は実績で先行しています。5G通信網を活用した遠隔手術は中国各地で試験的に行われており、2020年代に入って既に100件以上の遠隔ロボット手術が成功しています 。2023年には低軌道衛星ネットワークを介した遠隔手術まで登場し、地理的制約を超えた医療提供へのチャレンジが進んでいます(微創社の図邁ロボット使用)。これらはAI時代のスマート医療に向けた先駆的試みと言えるでしょう。
コストとアフターサービス
価格に関しては既に述べた通り、国産勢は概ね2~5割程度安価で、消耗品も低価格に抑えようとしています 。インテュイティブ社も対抗して価格引下げを行っていますが、それでも輸入機器特有のメンテナンス費などは割高になりがちです 。一方、中国企業は国内にサービス網を持ち、迅速な技術サポートを提供できる強みがあります。地理的に広大な中国において、故障時の対応やエンジニア派遣の速さは顧客満足度に直結します。この点で「現地生まれ」の企業は有利であり、地方の病院ほど国産機を選ぶ背景にもなっています 。最終的には、性能・安全性がほぼ互角になった段階で、価格とサービスの総合力勝負となるでしょう。
総じて、中国の手術用ロボット産業は「追いつき追い越せ」の局面に入っています。ダヴィンチを筆頭とする米国製品がいまだ高い壁として立ちはだかる一方、中国企業も政府支援を追い風に急速な技術進歩と市場開拓を進めています。日本企業に目を向ければ、川崎重工業のヒノトリはまず国内市場で症例実績を積みつつあり、今後アジア展開を狙う可能性もあります。中国政府の推進する国産化政策の下、今後数年で中国製ロボットのシェアがさらに伸びることは確実視されています。もっとも、国外市場で成功を収めるには製品の信頼性・ブランド力で依然としてインテュイティブ等に及ばず課題も多いのが実情です 。中国企業の中には東南アジアや欧州への進出を計画する動きもありますが 、各国の規制承認や販売ネットワーク構築には時間を要するでしょう。
まとめ
結論として、中国の手術用ロボット市場は政府支援と技術革新によって力強く成長しており、国内企業がダヴィンチ型ロボットの独占状態に挑んでいます。現状では性能面でほぼ肩を並べつつあり、価格優位性も武器に市場シェアを拡大中です。しかし、真の競争力という点では臨床実績や収益基盤で先行する海外企業にまだ分があります。中国各社がこのハードルを乗り越え、世界市場で存在感を示せるかどうか――その行方は、今まさに“手術ロボット大国”への転換期にある中国の医療イノベーションの成否にかかっていると言えるでしょう。
参考文献
- 手術支援ロボット「ダビンチ」、アジア太平洋最大の拠点が上海で稼働
- ダビンチに対抗する中国ベンチャー、手術支援ロボを割安に 海外進出も
- 現在の手術ロボット、将来的にはロボット外科医へ
- 香港の手術ロボットスタートアップCornerstoneがダ・ヴィンチに対抗する資金に注目
- 2024 年の中国の手術ロボット産業サプライチェーンにおける代表的な企業トップ 10
- 手術支援ロボットの「精鋒医療」が上場へ 世界的ライバル「ダヴィンチ」不在の中国市場で拡大狙う
- 外科手術ロボット「天璣」、手術を約8000件実施–人民網日本語版–人民日報
- 中国産「手術ロボット」、約10種が販売許可取得
- Tumai ®腹腔鏡手術ロボット
- AIがメスを担当、デジタル医療はどのような機会と課題に直面するのでしょうか?
- 手術ロボット市場が再び波紋を広げる
- 国産手術ロボットは価格競争を戦っている? 上海医療機器博覧会Medtecが詳しく説明します
- 中国産「手術ロボット」、約10種が販売許可取得
- 2025年腹腔鏡手術ロボット激戦:レオナルド・ダ・ヴィンチが防衛、国内「包囲」
- MedBot®
Xも日々更新しております!
最新記事掲載時は、Xでご案内いたします!
ぜひフォローを宜しくお願いします。