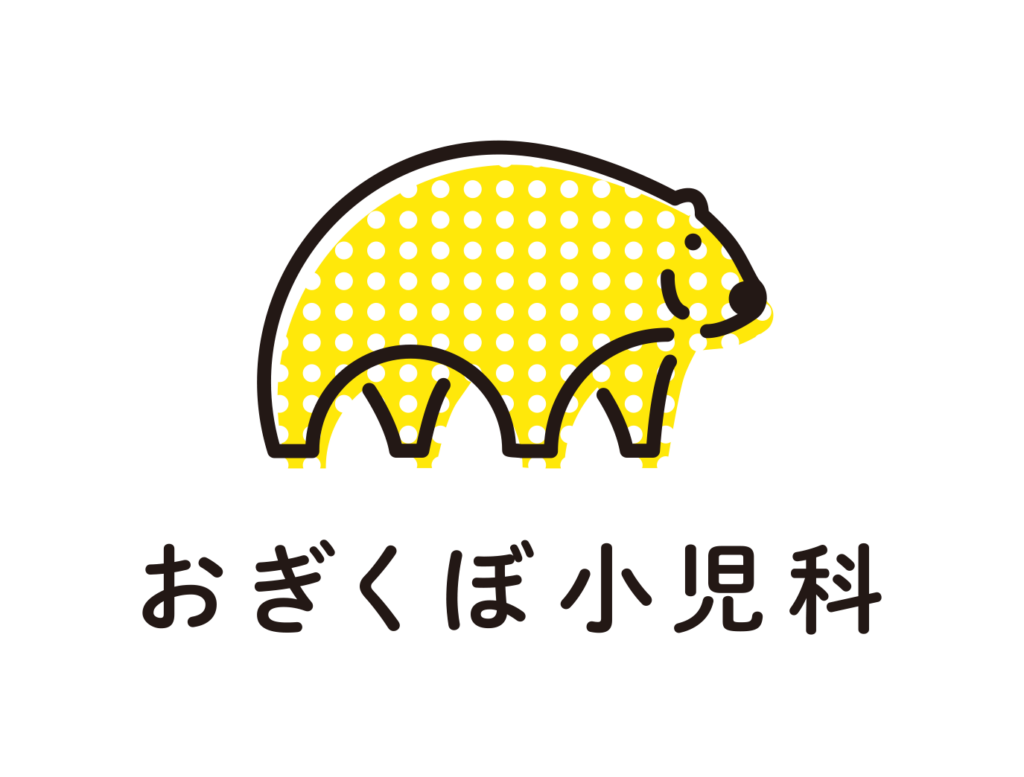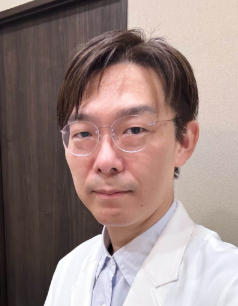なぜ医師が起業の道を選ぶのか
医師として培った専門性と経験を、より大きな社会課題の解決にチャレンジしたい。新しいキャリアに踏み出したい。そんな想いから起業の道を歩む医師が増えています。そこで、起業を迷うすべての人へ、救急医としてのバックグラウンドを持つ私が、なぜMBA取得後に起業という選択をしたのか、その理由と想いをお話しします。
救急医から起業家への転身
MBA取得という転機
救急医として現場で働く中で、医療現場の課題を根本的に解決するためには、医療技術だけでなく経営やビジネスの知識が必要だと痛感しました。とくに救急という職場は、救急搬送から退院調整まで、社会システムや病院経営に近い仕事が多いです。また私は災害医療の市民教育にも取り組んでいたために、より社会システムへの興味が強くなっていきました。その中で、医療政策を学ぶべくMBAへの進学を決めましたが、MBA取得は、医師としての専門性に加えて、組織運営や事業戦略の視点を身につける重要なステップでした。
起業という選択肢への迷い
MBA卒業後、進路選択では大きな迷いがありました。
選択肢として考えた道
- 臨床医への復帰:救急医として現場に戻り、直接的な患者ケアを継続
- 雇われ病院長:病院経営に携わりながら医療現場の改善を推進
- 行政職:医療政策の立案・実行に関わる道
- 戦略コンサルティング:医療を含めた多様な業種における経営改善支援
- 製薬:マーケティングや戦略の構築など
- 起業:自ら事業を立ち上げて社会課題解決に取り組む道
臨床医に戻ることは、患者さんと直接向き合える充実感がある一方で、個別の症例対応に留まってしまう限界を感じていました。雇われ病院長という道も、一つの医療機関の改善には貢献できますが、業界全体の構造的課題にアプローチするには制約があります。
それぞれに魅力があり、社会貢献の可能性を感じていましたが、最終的に起業を選んだ理由は、「楽しそう」「力がつきそう」という直感的な想いでした。この感覚は決して軽薄なものではなく、自分が最も情熱を注げる分野で、継続的に成長できる環境への憧れでした。
起業への原動力:社会に対する使命感
「力がある者の責任」という意識
現在起業に取り組む最大の動機は、「いろいろな経験をしてきた私にしかできない仕事がある。私が目の前の課題に取り組まずに誰がやるんだ」という強い使命感です。医師として培った専門知識、MBA で学んだビジネススキル、そして救急医時代に身につけた危機対応能力。これらの「力」を活用して社会課題に立ち向かうことは、自分にとって単なる選択肢ではなく、義務だと感じています。
医療従事者の課題に焦点を当てて
現在取り組んでいるのは、医療従事者が直面する問題の解決です。救急医時代に現場で感じた課題、同僚たちが抱える悩み、医療システム全体の構造的な問題。これらは単に「大変だ」で終わらせるのではなく、具体的なソリューションによって解決できるはずです。
医療業界が直面する構造的課題:
働き方改革への対応 医師の働き方改革により、2024年4月から医師にも時間外労働の上限規制が適用されました。しかし現場では、患者の安全を確保しながら労働時間を短縮する具体的な方法に苦慮しているのが現実です。単純な労働時間制限だけでは解決できない、業務効率化とシステム改革が急務です。
医師偏在問題の深刻化 都市部への医師集中と地方の医師不足は年々深刻化しています。特に救急医療においては、この偏在が患者の生命に直結する問題となっています。単に医師数を増やすだけでなく、適切な配置と働きやすい環境づくりが不可欠です。
社会保障費増大への対応 高齢化社会の進展により、医療費は毎年約1兆円ずつ増加しています。この増大する医療費を抑制しながら、質の高い医療を提供し続けるためには、効率化と価値向上の両立が求められています。
医療従事者個人が直面する課題
- 過重労働による燃え尽き症候群
- 医療事故や訴訟リスクへの不安
- キャリア形成の選択肢の限定性
- 急速に進歩する医療技術への対応負担
- 患者・家族とのコミュニケーション複雑化
- 電子カルテ導入等のIT化への適応
医師がビジネスに取り組む強みと課題
医師起業家の独自の強み
1. 深い現場理解と当事者意識 医師は医療現場の課題を皮膚感覚で理解しています。患者の痛み、医療従事者の負担、システムの非効率性を実体験として知っているからこそ、真のニーズに基づいたソリューションを設計できます。
2. 高度な問題解決能力 急性期医療などの現場では、限られた時間と情報の中で生命に関わる判断を下す訓練を積んでいます。この経験は、事業運営における迅速な意思決定と的確な問題解決に直結します。
3. 倫理観とミッション志向 医師として培った「患者第一」の価値観は、顧客中心のビジネス思考と親和性が高く、持続可能で社会意義のある事業創出につながります。
4. 高い信頼性と社会的権威 医師という資格や経験は、投資家、パートナー企業、顧客からの信頼獲得において大きなアドバンテージとなります。
5. 学習能力と専門性への適応力 医学は常に進歩する分野であり、医師は継続的な学習と新しい知識の習得に慣れています。この学習姿勢はビジネス分野でも活かされます。
医師がビジネスで直面する課題
1. ビジネススキルの不足 医学教育では財務、マーケティング、人事管理などのビジネススキルは学びません。MBA取得や実務経験を通じたキャッチアップが必要です。
2. リスク回避思考の強さ 医療現場では「安全第一」が最優先されますが、ビジネスでは適度なリスクテイクが成長に不可欠です。この思考転換には時間がかかります。
3. 時間管理の制約 臨床業務を継続しながらの起業は、時間的制約が大きな障壁となります。どちらも中途半端になるリスクを避けるため、優先順位の明確化が重要です。
4. 医療業界の保守性 医療業界は規制が厳しく、変化に対して慎重な姿勢があります。イノベーションの導入には、業界の理解と長期的な視点が必要です。
5. 収益モデルの理解不足 医師は「治療」に対する対価という単純な収益構造に慣れているため、複雑なビジネスモデルやマルチステークホルダーとの関係性理解に時間がかかることがあります。
医師起業家として目指すもの
医療現場の声を事業化へ
医師だからこそ理解できる現場のニーズがあります。患者さんの苦痛、医療従事者の負担、医療制度の矛盾。これらを肌で感じた経験を持つ医師が起業することで、真に現場に必要とされるソリューションを生み出せると確信しています。
臨床現場に潜む起業アイデアの実例
実際に医師として働く中で、「これがあったらいいのに」と感じる場面は数え切れません。そして実際に、多くの医師起業家がこうした現場の課題を解決するサービスを立ち上げています。以下は、医療現場の具体的な課題解決に取り組む、比較的新しいスタートアップの例です。
1. 遠隔心臓リハビリアプリ「CaTe」(株式会社CaTe)
現在も藤田保健衛生大学病院でカテーテル治療にも従事する循環器内科医として勤務している寺嶋一裕氏が2020年3月に創業したCaTeは、心疾患患者が自宅で心臓リハビリテーションを行える治療用アプリを開発しています。
日本では外来心臓リハビリへの参加率が約7%と低く、心不全患者の多くが再入院を繰り返している現状を受け、スマートフォンとApple Watchを活用して安全で効果的な心臓リハビリを自宅で実施できるシステムを構築しました。2023年には4億8000万円のシリーズA資金調達を実施し、藤田医科大学病院で医師主導試験も開始されています。現在は運動療法に加え、バイタルデータ共有、生活食事管理、AIによる通知・チャット機能など包括的な心臓リハビリテーションの提供を目指しています。
2. 認知症予防「BrainSuite」(株式会社CogSmart)
東北大学加齢医学研究所発のスタートアップとして2019年に設立されたCogSmartは、「早期段階からの認知症予防」を目指しています。代表取締役を務める瀧靖之氏は東北大学加齢医学研究所の教授でもあり、長年にわたって脳科学・認知症研究に従事してきました。同社が開発した脳ドック用ソフトウェア「BrainSuite」は、頭部MRI画像のAI解析により記憶をつかさどる海馬の萎縮度を評価し、30代から70代までを対象として個別の予防行動を提示することで、将来の認知症リスク低減を促します。2022年にはシリーズAで3.5億円を調達し、全国の脳ドック対応病院に提供を拡大しています。海馬は早い人では30代から萎縮が始まり、生活習慣により萎縮が加速することが分かっており、早期の介入で予防効果が期待できる点に着目したサービスです。
3. 医師採用プラットフォーム「Med-Pro Doctors」(株式会社EN)
医師・薬剤師・MBAの資格を持つ鎌形博展氏(本記事の執筆者です)が2023年1月に創業した株式会社ENは、医師採用プラットフォーム「Med-Pro Doctors」を運営しています。鎌形氏は東京医科大学救急災害医学講座に在籍中に慶應義塾大学大学院経営管理研究科とDartmouth Collegeで医療政策・経営管理を学び、その後複数の医療ベンチャーや医療法人の立ち上げを経験した医師起業家です。医療業界では高額な仲介手数料やアンマッチな紹介が繰り返され、人材の循環が滞っている課題に着目し、医師と医療機関が直接マッチングできる完全無料の求人プラットフォームを開発しました。独自の評価システムにより医師と医療機関の信頼性を可視化し、より良いマッチングを実現しています。2023年11月のβ版リリースから1か月で医師ユーザー1000人、医療機関250施設超が登録し、現在は医師1,500名以上、医療機関800施設以上が利用している急成長中のサービスです。資金調達はせず、周辺ビジネスにより事業化を目指しています。このメディアも本事業に関連して運営しております。
これらのスタートアップは全て、医師が実際の臨床現場で直面した課題を解決するために生まれました。医療スタートアップでの成功事例はまだまだ多くはないのが現状ですが、これからの日本の未来を作る素晴らしい取り組みがどんどん現れてきています。
持続可能な社会貢献のために
慈善活動や一時的な支援ではなく、ビジネスとして持続可能な形で社会課題を解決すること。これが起業という手段を選んだ理由です。例外を除き、良いサービス、社会的価値のある事業でなければ、ビジネスとしては成立しません。事業として成立することで、より多くの人に価値を提供し、長期的な社会変革を実現できます。
これから起業を考える医師へのメッセージ
医師として培った能力は、起業においても大きな武器となります。患者さんの命に関わる判断を日常的に行ってきた経験、限られた時間で最適解を導き出す能力、チーム医療でのリーダーシップ。これらのスキルは、事業運営において必ず活かされます。
もし今、起業に興味を持ちながらも迷っているなら、「なぜ自分が起業したいのか」という根本的な動機を明確にすることから始めてください。私の場合、それは「社会を良くするために戦う」という使命感でした。
医師だからこそ見える課題、医師だからこそ解決できる問題がある。その認識を持って行動を起こすことで、医療界そして社会全体により大きな価値を提供できるはずです。
著者
鎌形博展 医師、株式会社EN 代表取締役、医療法人社団季邦会 理事長、東京医科大学病院 非常勤医師

東京都出身。埼玉県育ち。
明治薬科薬学部を卒業後、中外製薬会社でMRとなるも、友人の死をきっかけに脱サラして、北里大学医学部へ編入する。
卒業後は東京医科大学病院救命救急センターにて救急医として従事。2017年には慶應義塾大学大学院にて医療政策を学び、MBAを取得。東北大学発医療AIベンチャー、東京大学発ベンチャーを起業した他、医療機器開発や事業開発のコンサルティングも経験。2019年、うちだ内科医院を継承開業。以降、2020年に医療法人季邦会(美谷島内科呼吸器科医院)を継承し、2021年には街のクリニック 日野・八王子を新規開業。2023年には株式会社EN創業。国際緊急援助隊隊員・東京DMAT隊員・社会医学系専門医。趣味はBBQ。43歳で剣道・フェンシングを再開