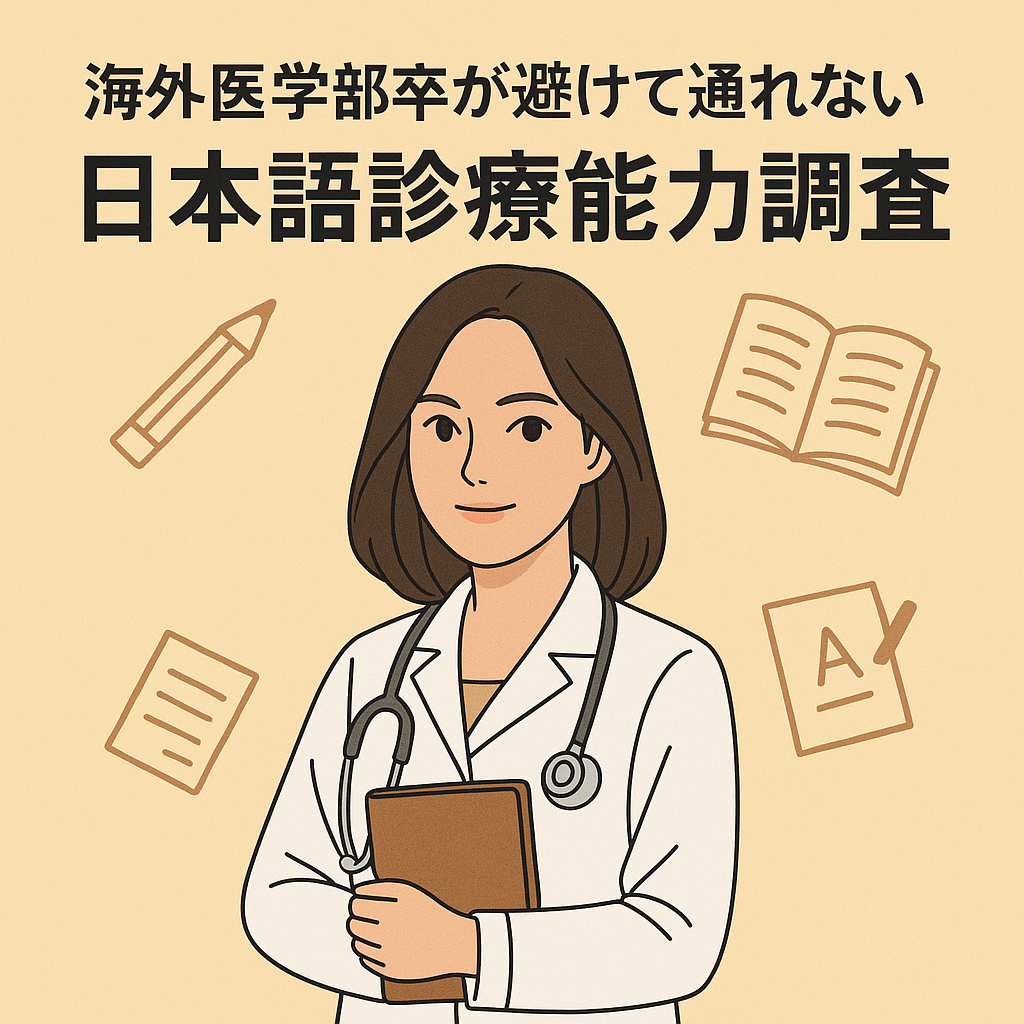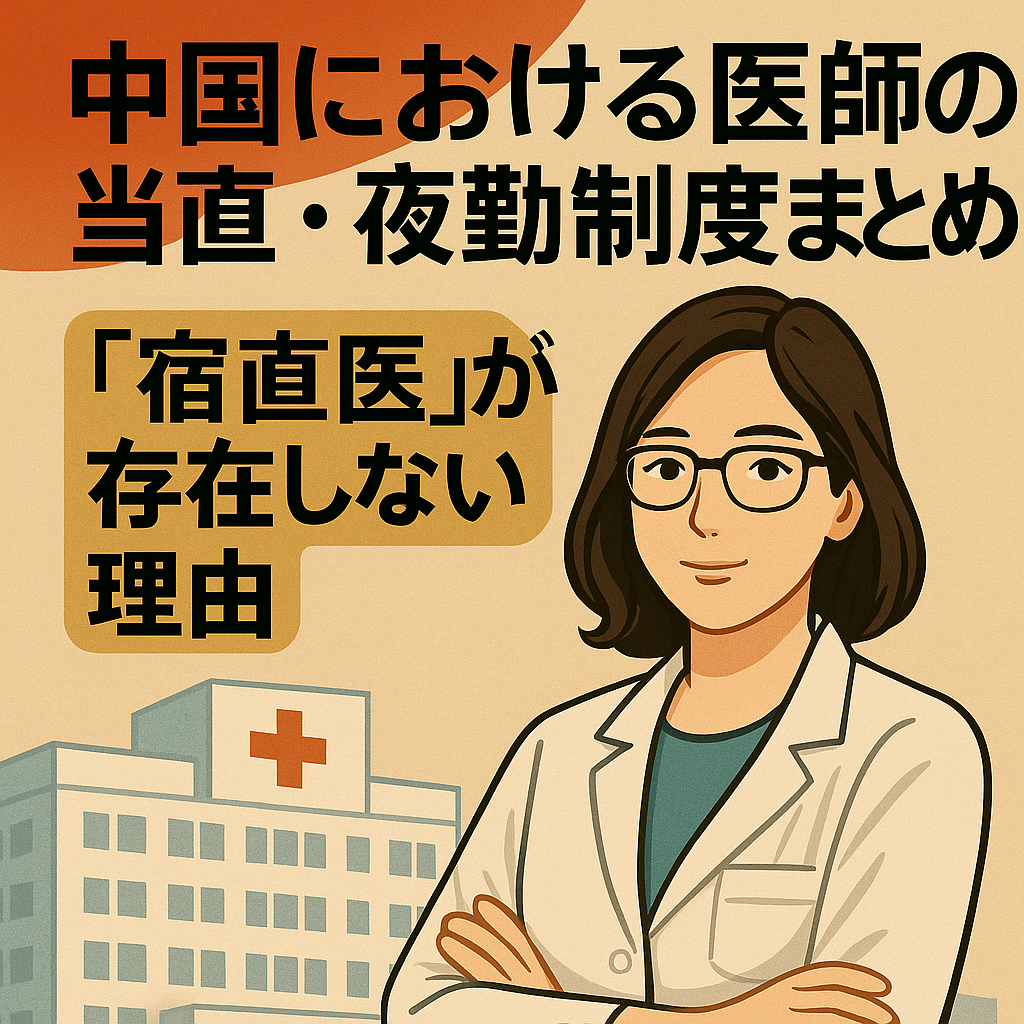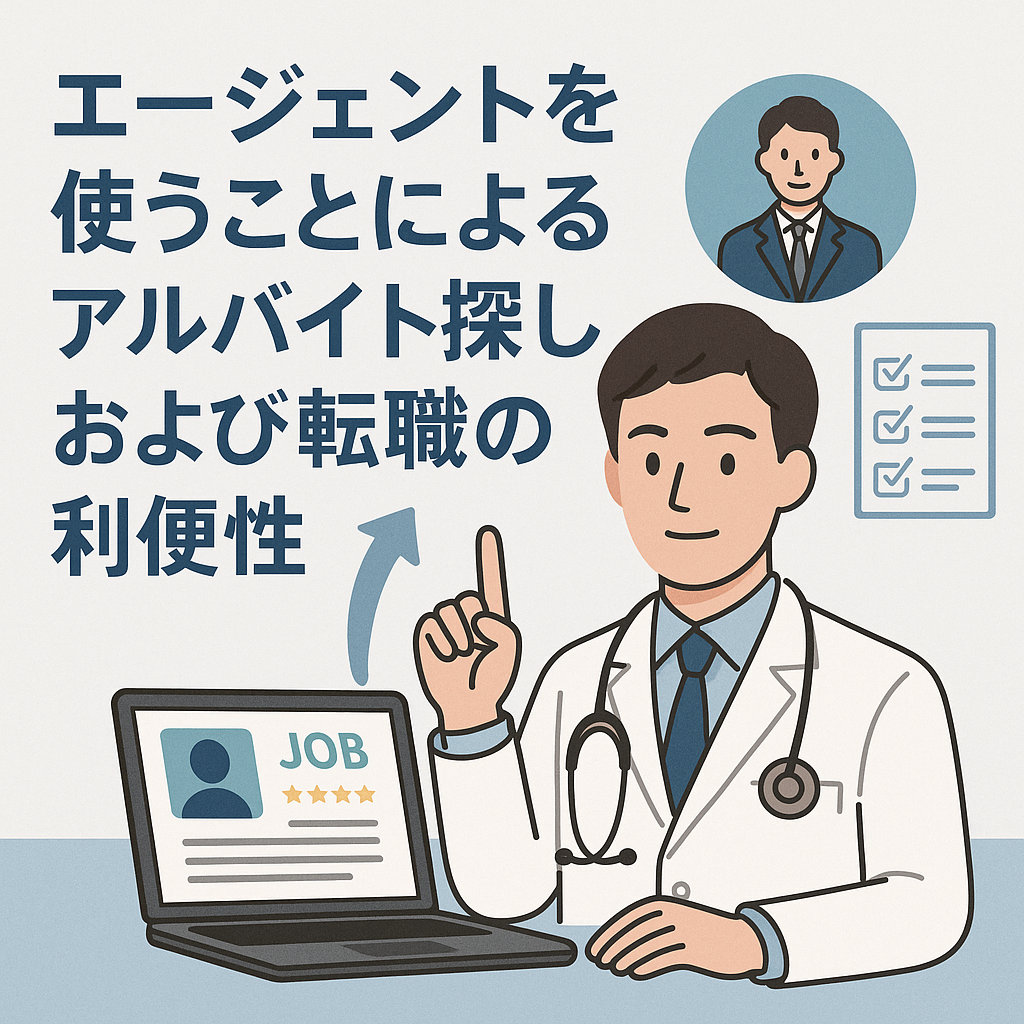こんにちは、今日は若手医師の皆さん向けの記事です。今、日本の医療制度は大きな変革期を迎えています。皆さんが今後キャリアを積んでいく中で直面するであろう医療提供体制の変化について、最新の財政資料をもとにお伝えしたいと思います。2025年4月の財務省における分科会の議事録を参考にしてます。
社会保障制度の現状と課題
まず知っておいていただきたいのは、日本の社会保障関係費が急速に増加している現実です。平成24年度には約28.9兆円だった社会保障関係費は、令和7年度には約38.3兆円へと拡大しています。特に医療・介護の給付費用は過去20年でほぼ倍増し、経済成長率を大きく上回るペースで増加を続けています。
この費用の約半分は保険料によって賄われていますが、少子高齢化が進む中で、現役世代の保険料負担はすでに限界に近づいています。協会けんぽの保険料率は2000年の13.58%から2040年には32.6%にまで上昇すると推計されており、このままでは現役世代の手取り収入がますます減少してしまいます。
このような状況を踏まえ、政府は「質の高い医療・介護の効率的な提供」「保険給付範囲の適切な設定」「負担の公平化」という3つの視点から改革を進めようとしています。若手医師の皆さんにとって特に関係の深い医療提供体制の改革について詳しく見ていきましょう。
医療提供体制の変革と若手医師のキャリアへの影響
これからの医療提供体制は「2040年に向けた新たな地域医療構想」によって大きく変わっていく予定です。2025年に関連法案が国会に提出される見込みですが、その方向性はすでに明らかになっています。
特に注目すべきは、病床の機能分化・連携にとどまらず、外来・在宅医療、介護連携も含めた包括的な医療提供体制が構築されようとしている点です。「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担が一層明確化され、「急性期拠点機能」「高齢者救急・地域急性期機能」「在宅医療等連携機能」「専門等機能」「医育及び広域診療機能」といった機能別の位置づけが進められます。
若手医師の皆さんは、自分のキャリアを考える際に、こうした医療機関の機能分化の方向性を意識しておくことが大切です。例えば高度急性期を志向するのか、あるいは地域包括ケアの中で慢性期・回復期医療に携わりたいのか、専門医としてのキャリアをどう形成していくかなど、今後の医療提供体制の変化を見据えた進路選択が求められるでしょう。
また、医師偏在対策も強化されます。「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」の実行・具体化が進められ、診療科間、地域間の偏在是正のための対策が講じられます。特に都市部への医師集中を是正するための経済的インセンティブや規制的手法の強化が検討されており、若手医師の勤務地選択にも影響を与える可能性があります。
診療報酬改定の方向性と求められる診療スタイルの変化
次に、2026年度の診療報酬改定の方向性についてお伝えしましょう。この改定では、「地域での全人的なケアの実現」に資する報酬体系への転換が進められます。
具体的には、かかりつけ医機能を適切に評価する報酬体系への見直しが検討されています。現在の「機能強化加算」や「地域包括診療料・加算」などが再編され、地域の患者を「治し、支える」役割を的確に評価する体系が構築される見込みです。
また、生活習慣病管理においては、診療ガイドラインと整合性のある報酬体系への見直しが検討されています。例えば、血圧がコントロールされている高血圧患者に対する生活習慣病管理料の算定頻度を見直すなど、より効率的な疾病管理が求められるようになるでしょう。
若手医師の皆さんには、こうした「量」よりも「質」を重視する診療スタイルへの転換が求められます。患者一人ひとりの状態に応じた適切な管理を行いながら、無駄のない効率的な医療提供を心がけることが重要になってくるでしょう。
薬剤処方をめぐる変化とデータ活用の推進
薬剤処方に関する改革も見逃せません。リフィル処方箋の推進や、OTC類似薬の保険給付見直しなど、処方のあり方そのものを見直す改革が進められようとしています。
特に重要なのは、費用対効果評価の活用拡大です。高額医薬品の保険収載や価格調整において、費用対効果の視点がより強く反映されるようになります。また、地域フォーミュラリ(地域で推奨される医薬品リスト)の普及も促進され、経済性も考慮した標準的な薬物治療の確立が目指されています。
若手医師の皆さんには、常に最新のエビデンスと費用対効果の視点を持ち、患者にとって最適な処方を考える姿勢が求められるでしょう。また、不必要な多剤・重複投薬を避け、必要に応じて減薬・休薬も考慮した患者本位の治療を行うことも重要になります。
さらに、医療DXの推進により、診療データの活用が進められます。診療ガイドラインの策定や医療の質評価にもデータが活用される時代になりつつあり、若手医師の皆さんにはデータリテラシーを高め、エビデンスに基づく医療を実践する力が求められるでしょう。
高齢者医療と負担の公平化
高齢化が進む中で、年齢ではなく能力に応じた負担の公平化も進められます。特に後期高齢者医療制度では、金融所得・資産の勘案や「現役並み所得」判定基準の見直しが検討されています。
また、高齢者が活躍する長寿社会にふさわしい高齢者医療制度の在り方も検討されており、医療提供側としても、高齢者の多様なニーズに応じた医療提供が求められるようになるでしょう。
若手医師の皆さんには、高齢者医療の特性を理解し、単に病気を治すだけでなく、患者の生活全体を支える視点を持った診療が期待されます。また、医療と介護の連携についても理解を深め、地域包括ケアシステムの中で医師としての役割を果たすことが求められるでしょう。
若手医師へのメッセージ:変化を恐れず、医療の質を高める担い手に
ここまで様々な改革の方向性をお伝えしてきましたが、これらはすべて「持続可能な医療制度の構築」と「質の高い医療の提供」という目標に向けたものです。確かに変化は不安を伴いますが、若手医師の皆さんには、こうした改革を前向きに捉え、新しい医療提供体制の中でリーダーシップを発揮していただきたいと思います。
特に重要なのは、専門性を高めながらも、患者を全人的に捉える視点を失わないことです。どんなに医療が高度化・専門化しても、最終的には「患者のために何ができるか」という原点に立ち返ることが大切です。また、チーム医療の重要性がますます高まる中で、多職種との連携力も欠かせません。
社会保障制度が大きく変わろうとしている今、若手医師の皆さんには、変化を恐れず、むしろ新しい医療の在り方を切り拓く担い手となることを期待されています。患者のために最善を尽くすという医師の本分を守りながら、効率的で質の高い医療提供体制の構築に貢献していただければと思います。
皆さんの活躍が、これからの日本の医療を支える大きな力になるに違いありません。
2025/04/25
著者:鎌形博展
医師、株式会社EN 代表取締役、医療法人社団季邦会 理事長、東京医科大学病院 非常勤医師

東京都出身。埼玉県育ち。
明治薬科薬学部を卒業後、中外製薬会社でMRとなるも、友人の死をきっかけに脱サラして、北里大学医学部へ編入する。
卒業後は東京医科大学病院救命救急センターにて救急医として従事。2017年には慶應義塾大学大学院にて医療政策を学び、MBAを取得。東北大学発医療AIベンチャー、東京大学発ベンチャーを起業した他、医療機器開発や事業開発のコンサルティングも経験。2019年、うちだ内科医院を継承開業。以降、2020年に医療法人季邦会(美谷島内科呼吸器科医院)を継承し、2021年には街のクリニック 日野・八王子を新規開業。2023年には株式会社EN創業。国際緊急援助隊隊員・東京DMAT隊員・社会医学系専門医指導医。趣味はBBQ。43歳で剣道・フェンシングを再開。