胸痛は日常診療において最も慎重な対応が求められる症状の一つです。生命に直結する疾患から軽微な症状まで幅広い病態が胸痛として現れるため、適切な初期評価と迅速な判断が患者の予後を大きく左右します。本ガイドでは、胸痛患者の初期診療における体系的なアプローチを詳しく解説し、見逃してはならない危険な兆候から適切な治療方針まで、実践的な知識を提供いたします。
胸痛初期評価の基本的アプローチ
胸痛患者が来院した際の初期対応は、生命の危機に直結する可能性の迅速な評価から始まります。患者の第一印象、バイタルサイン、症状の重篤度を総合的に判断し、救急診療が必要か通常の内科診療で対応可能かを瞬時に決定する必要があります。
生命危機の可能性が高い場合の対応
患者の状態が生命の危機に直結する可能性が高いと判断された場合は、直ちに救急診療の進め方に切り替えます。まずABCDの確保を最優先に行い、気道の確保、呼吸の確認、循環状態の評価、意識レベルの確認を迅速に実施します。
同時進行で心電図モニタリングを開始し、胸部単純X線撮影を手配します。技術的に可能であれば経胸壁心エコー検査を実施し、心臓の動きや心嚢液貯留の有無を確認します。これらの基本的検査により、急性心筋梗塞、心タンポナーデ、大動脈解離などの致命的疾患のスクリーニングを行います。
自院での対応が困難と判断される場合は、速やかに救急搬送を手配します。搬送中の患者管理も重要で、必要に応じて酸素投与、静脈路確保、心電図モニタリングの継続を行います。
自院で対応可能と判断される場合でも、循環器専門医や救急医への早急な相談を行い、専門的な指示に従って鎮痛、鎮静、酸素投与などの初期治療を実施します。
比較的安定した患者への対応
幸いにして生命に関わる緊急性が低いと判断される場合は、より詳細で体系的な診療を進めます。しかし、胸痛の特徴として、症状の重篤さと疾患の重要度が必ずしも比例しないことを常に念頭に置く必要があります。
胸痛は本質的に主観的な体験であり、患者によって表現方法が大きく異なります。「胸の痛み」と明確に表現する患者もいれば、「胸の違和感」「圧迫感」「締め付けられる感じ」「息苦しさ」「胸が重い」など、様々な表現で症状を訴える患者もいます。
患者の訴えを丁寧に聞き取り、痛みの性質(鈍痛、鋭い痛み、焼けるような痛み、締め付けられるような痛み)、痛みの部位(前胸部、側胸部、背部への放散の有無)、持続時間(瞬間的、数分間、数時間継続)、発症のきっかけや誘因(労作時、安静時、体位変換時、深呼吸時)、随伴症状の有無(呼吸困難、動悸、冷汗、悪心嘔吐、失神)などを詳細に確認します。
胸痛の包括的鑑別診断
胸痛を引き起こす疾患は極めて多岐にわたり、循環器疾患、呼吸器疾患、消化器疾患、整形外科的疾患、神経系疾患、精神的要因など、様々な臓器系統が関与します。診断的アプローチでは、生命予後への影響度に基づいた優先順位付けが重要です。
生命予後に直接関与する重篤疾患
急性冠症候群(急性心筋梗塞・不安定狭心症)
急性冠症候群は胸痛の原因として最も重要な疾患の一つです。典型的には前胸部の圧迫感として現れ、左肩、左腕、下顎、背部への放散痛を伴うことがあります。安静時にも症状が持続し、冷汗、悪心、嘔吐、失神などの随伴症状を認めることが多いです。
心電図でのST変化、血液検査でのトロポニンやCK-MBの上昇が診断の手がかりとなります。ただし、糖尿病患者や高齢者では典型的な症状を示さない場合があり、より慎重な評価が必要です。
胸部大動脈解離
突然発症する激烈な胸背部痛が特徴的で、患者は「今まで経験したことのない痛み」と表現することが多いです。痛みは背部から腹部へと移動することがあり、解離の進展を反映します。
血圧左右差、脈拍左右差、大動脈弁逆流による拡張期雑音、神経学的異常などの身体所見が重要な手がかりとなります。造影CTや経胸壁心エコーによる迅速な画像診断が必要です。
肺塞栓症
突然発症する胸痛と呼吸困難が主症状で、特に深呼吸時に胸痛が増強することが特徴的です。長期臥床、手術歴、癌の既往、経口避妊薬服用などのリスクファクターの存在が診断の手がかりとなります。
D-ダイマーの上昇、動脈血ガス分析での酸素化不良、心エコーでの右心負荷所見などが診断の補助となります。確定診断には造影CTまたは肺血流シンチグラフィが必要です。
心タンポナーデ
心嚢内への液体貯留により心臓の拡張が制限される状態で、頸静脈怒張、血圧低下、心音減弱(Beck三徴)が典型的な所見です。心エコーによる心嚢液の確認と右室虚脱の評価が診断に重要です。
気胸(特に緊張性気胸)
突然発症する胸痛と呼吸困難が主症状で、特に若い男性に多く見られます。緊張性気胸では血圧低下、頸静脈怒張、気管偏位などの重篤な循環動態への影響が現れます。
胸部X線での肺虚脱の確認が診断に重要ですが、緊張性気胸が疑われる場合は画像確認を待たずに胸腔穿刺による減圧を行う必要があります。
特発性食道破裂(Boerhaave症候群)
激しい嘔吐後に発症する激烈な胸痛が特徴的で、縦隔気腫を伴うことが多いです。胸部X線での縦隔陰影の拡大、造影CTでの食道壁の断裂確認が診断に重要です。
その他の循環器疾患
急性心膜炎
胸骨後面の鋭い痛みが特徴的で、前屈位で軽減し、仰臥位で増悪することが多いです。発熱を伴うことが多く、心電図でのST上昇(凹型)、心嚢液貯留の有無を心エコーで評価します。
急性心筋炎
胸痛に加えて心不全症状を呈することがあり、ウイルス感染の既往歴が診断の手がかりとなります。心電図異常、心筋逸脱酵素の上昇、心エコーでの壁運動異常などが認められます。
不整脈
動悸に伴う胸部不快感として現れることが多く、24時間心電図モニタリングによる不整脈の記録が診断に重要です。
たこつぼ型心筋症
強いストレス後に発症することが多く、急性心筋梗塞様の症状と心電図変化を示しますが、冠動脈に有意狭窄を認めないことが特徴的です。
循環器以外の胸郭内疾患
胸膜炎
深呼吸や咳嗽時に増悪する鋭い胸痛が特徴的で、胸膜摩擦音の聴取、胸部X線での胸水貯留の確認が診断の手がかりとなります。
縦隔気腫
胸骨後面の痛みと呼吸困難が主症状で、頸部皮下気腫を伴うことがあります。胸部X線での縦隔陰影の変化や皮下気腫の確認が重要です。
逆流性食道炎
胸骨後面の焼けるような痛みが特徴的で、食後や仰臥位で症状が増悪します。プロトンポンプ阻害薬の試験的投与による症状改善が診断的価値を持ちます。
その他の疾患
消化器疾患
消化性潰瘍では心窩部痛として現れることが多いですが、上部消化管の病変では胸痛として認識されることがあります。胆石症や急性膵炎でも、痛みが上腹部から胸部に放散することがあります。
帯状疱疹
一側性の神経支配領域に沿った痛みが特徴的で、初期には皮疹が明らかでない場合があります。痛みの性質は神経痛様で、体表面の知覚異常を伴うことが多いです。
肋間神経痛
体位変換や深呼吸により増悪する一側性の鋭い痛みが特徴的で、肋間神経の走行に沿った圧痛を認めることがあります。
心臓神経症
器質的異常を伴わない機能性の胸痛で、ストレスや精神的要因が関与することが多いです。除外診断として位置づけられ、十分な検査による器質的疾患の除外が必要です。
危険な徴候(レッドフラッグ)の識別
胸痛診療において、重篤な疾患の可能性を示唆する警告信号(レッドフラッグ)を迅速に識別することは、患者の生命予後に直結する重要なスキルです。以下の徴候が認められる場合は、緊急性の高い疾患を強く疑い、迅速な対応が必要です。
発症様式に関するレッドフラッグ
突然発症
「雷鳴様」と表現されるような突然の激烈な胸痛は、大動脈解離、肺塞栓症、特発性食道破裂などの可能性を強く示唆します。患者が痛みの開始時刻を明確に記憶している場合は、特に注意が必要です。
急性発症
数分から数時間で急速に悪化する胸痛も、急性冠症候群、急性心膜炎、気胸などの重篤な疾患の可能性があります。症状の進行パターンを詳細に聴取することが重要です。
痛みの特徴に関するレッドフラッグ
痛みの放散や移動
胸痛が左肩、左腕、下顎、背部へ放散する場合は急性冠症候群を強く疑います。また、胸部から背部、さらに腹部へと痛みが移動する場合は大動脈解離の進展を示唆します。
今までに経験したことのない痛み
患者が「今まで経験したことのない激しい痛み」と表現する場合は、大動脈解離、急性心筋梗塞、肺塞栓症などの重篤な疾患を強く疑う必要があります。
随伴症状に関するレッドフラッグ
自律神経症状
冷汗、顔面蒼白、嘔気、嘔吐などの自律神経症状は、急性冠症候群の重要な随伴症状です。特に冷汗を伴う胸痛は緊急性が高いと判断します。
循環動態への影響
血圧低下、頻脈、不整脈、失神などの循環動態への影響は、心タンポナーデ、緊張性気胸、大量肺塞栓症、急性心筋梗塞などの可能性を示唆します。
呼吸困難
胸痛に伴う呼吸困難は、肺塞栓症、気胸、急性心不全、急性心筋梗塞などの可能性を示唆します。特に安静時の呼吸困難は重篤度が高いと判断します。
意識レベルの変化
意識混濁、失神、けいれんなどの神経症状は、重篤な循環不全や脳血管障害の合併を示唆し、緊急対応が必要です。
時間経過に関するレッドフラッグ
3週間以上持続する症状
長期間持続する胸痛と咳嗽の組み合わせは、肺癌、結核、慢性感染症などの可能性を示唆します。また、慢性的な胸痛でも急激な悪化がある場合は緊急疾患を考慮します。
胸膜炎性胸痛の特徴
深呼吸、咳嗽、体位変換により明らかに増悪する胸痛は胸膜炎を示唆し、感染性、悪性、自己免疫性などの原因の精査が必要です。
体系的な診断アプローチ
胸痛の正確な診断には、詳細な病歴聴取、系統的な身体診察、適切な検査の組み合わせが必要です。各段階で得られた情報を統合し、鑑別診断を絞り込んでいきます。
病歴聴取の重点項目
痛みの詳細な特徴
疼痛の部位、性質、強度、持続時間、誘発因子、軽快因子を詳細に聴取します。VAS(Visual Analog Scale)を用いた客観的な疼痛評価も有用です。
既往歴と危険因子
冠危険因子(高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、家族歴)、血栓症リスク(悪性腫瘍、手術歴、長期臥床、経口避妊薬)、自己免疫疾患、感染症の既往などを確認します。
服薬歴
抗凝固薬、抗血小板薬、降圧薬、利尿薬、ステロイド、化学療法薬などの服薬状況は、鑑別診断や治療選択に重要な情報となります。
系統的身体診察
全身状態の評価
意識レベル、血圧、脈拍、呼吸数、体温、酸素飽和度などのバイタルサインを正確に測定し、ショック状態の有無を評価します。
心血管系の診察
頸静脈怒張、心音(強さ、リズム、雑音)、末梢脈拍(強さ、左右差)、下肢浮腫の有無を系統的に評価します。大動脈弁逆流を示唆する拡張期雑音の聴取は特に重要です。
呼吸器系の診察
胸郭の動き、呼吸音(左右差、異常音)、胸膜摩擦音、皮下気腫の有無を詳細に評価します。
腹部の診察
上腹部痛として現れる胸痛の鑑別のため、腹部の圧痛、筋性防御、腸音の評価を行います。
神経学的診察
大動脈解離に伴う神経症状、脳血管障害の合併を評価するため、意識レベル、四肢の運動・感覚機能を確認します。
検査戦略と解釈
血液検査
心筋逸脱酵素(トロポニン、CK-MB)、炎症反応(白血球数、CRP)、凝固系(PT、APTT、D-ダイマー)、腎機能、電解質、血糖値を評価します。特にトロポニンは急性冠症候群の診断に極めて重要です。
心電図検査
12誘導心電図を速やかに実施し、ST変化、異常Q波、不整脈、心膜炎を示唆するST上昇などを評価します。前回の心電図との比較も重要な情報となります。
胸部X線検査
肺野の透過性(気胸)、心陰影(心拡大、心嚢液)、縦隔陰影(大動脈解離、縦隔気腫)、胸水の有無を評価します。
心エコー検査
壁運動異常、弁膜症、心嚢液貯留、右心負荷所見を評価し、急性冠症候群、心タンポナーデ、肺塞栓症の診断に有用です。
高次画像検査
造影CTは大動脈解離、肺塞栓症の確定診断に必須です。MRIは大動脈解離の評価や心筋症の診断に有用ですが、緊急時には撮影時間が長いため制限があります。
治療戦略と緊急対応
胸痛の治療は原因疾患の特定と、それに応じた適切な治療の実施が基本となります。診断が確定するまでの対症療法と、確定診断後の根本的治療の両方を適切に行う必要があります。
診断確定前の対症療法
疼痛管理
診断が確定するまでの間、適切な疼痛コントロールは患者の苦痛軽減と循環動態の安定化に重要です。アセトアミノフェンは副作用が少なく、最初の選択肢として適しています。
オピオイド系鎮痛薬は強い疼痛に対して効果的ですが、呼吸抑制、血圧低下、意識レベル低下のリスクがあるため、慎重な使用が必要です。特に高齢者や呼吸器疾患のある患者では注意が必要です。
NSAIDsは抗炎症作用があり心膜炎などには有効ですが、急性冠症候群では心血管イベントのリスクを増加させる可能性があるため、診断確定前の使用は避けるべきです。
酸素療法
酸素飽和度が低下している場合や呼吸困難を認める場合は、適切な酸素投与を行います。ただし、COPD患者では高濃度酸素による炭酸ガス蓄積に注意が必要です。
循環管理
血圧低下や頻脈を認める場合は、輸液や昇圧薬の使用を検討しますが、心不全や大動脈解離では血圧管理が重要であり、降圧療法が必要な場合もあります。
特定疾患に対する治療
急性冠症候群
抗血小板療法(アスピリン、クロピドグレル)、抗凝固療法(ヘパリン)、ニトログリセリン、β遮断薬などの薬物療法に加えて、重症例では緊急冠動脈造影とPCI(経皮的冠動脈インターベンション)が必要です。
大動脈解離
血圧管理が最重要で、収縮期血圧を100-120mmHgにコントロールします。Stanford A型では緊急手術、Stanford B型では保存的治療が基本ですが、合併症により手術適応となる場合があります。
肺塞栓症
抗凝固療法(ヘパリン、ワルファリン、DOAC)が基本で、重症例では血栓溶解療法や外科的血栓除去術が必要です。
気胸
軽度の場合は経過観察、中等度以上では胸腔ドレナージが必要です。緊張性気胸では緊急的な胸腔穿刺による減圧が生命救済に重要です。
感染性疾患
肺炎や胸膜炎では適切な抗生物質の選択と投与が重要です。起炎菌の推定と薬剤感受性を考慮した治療選択を行います。
患者教育と予防戦略
生活習慣の改善
冠危険因子の管理(禁煙、血圧・血糖・脂質の管理)、適度な運動、ストレス管理の重要性を説明します。
症状の自己管理
緊急受診が必要な症状の説明、ニトログリセリンの適切な使用法、日常生活における注意点を指導します。
定期的な経過観察
慢性疾患の管理、定期検査の重要性、薬物治療のアドヒアランス向上を図ります。
まとめ:胸痛診療の要点
胸痛は多様な病態を示す症状であり、生命に関わる緊急疾患から軽微な症状まで幅広い鑑別診断が必要です。重要なのは、レッドフラッグを見逃さない迅速な初期評価と、体系的な診断アプローチによる正確な診断です。
特に急性冠症候群、大動脈解離、肺塞栓症などの重篤疾患は、早期診断と適切な治療により患者の予後が大きく改善されます。一方で、機能性疾患や軽微な疾患についても、患者の不安を軽減し、適切な説明と指導を行うことが重要です。
継続的な医学教育と臨床経験の蓄積により、胸痛患者に対するより良い医療を提供していくことが求められます。
著者:鎌形博展
医師、株式会社EN 代表取締役、医療法人社団季邦会 理事長、東京医科大学病院 非常勤医師

東京都出身。埼玉県育ち。
明治薬科薬学部を卒業後、中外製薬会社でMRとなるも、友人の死をきっかけに脱サラして、北里大学医学部へ編入する。
卒業後は東京医科大学病院救命救急センターにて救急医として従事。2017年には慶應義塾大学大学院にて医療政策を学び、MBAを取得。東北大学発医療AIベンチャー、東京大学発ベンチャーを起業した他、医療機器開発や事業開発のコンサルティングも経験。2019年、うちだ内科医院を継承開業。以降、2020年に医療法人季邦会(美谷島内科呼吸器科医院)を継承し、2021年には街のクリニック 日野・八王子を新規開業。2023年には株式会社EN創業。国際緊急援助隊隊員・東京DMAT隊員・社会医学系専門医。趣味はBBQ。43歳で剣道・フェンシングを再開




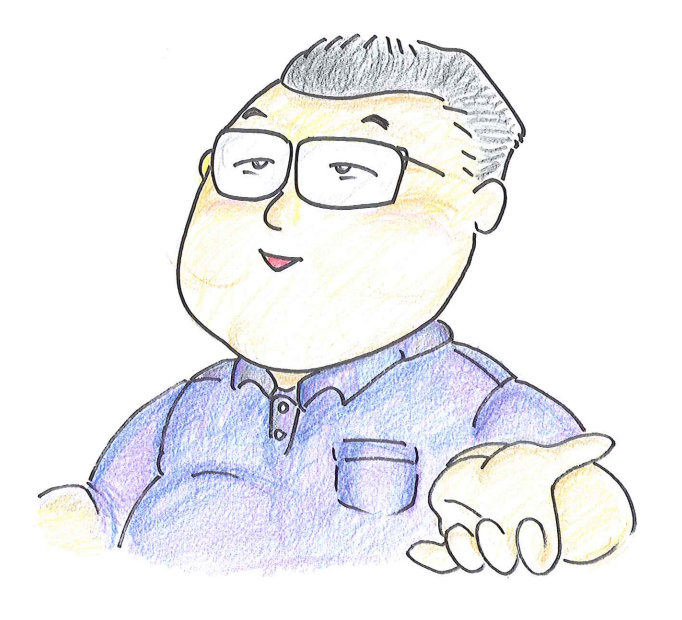
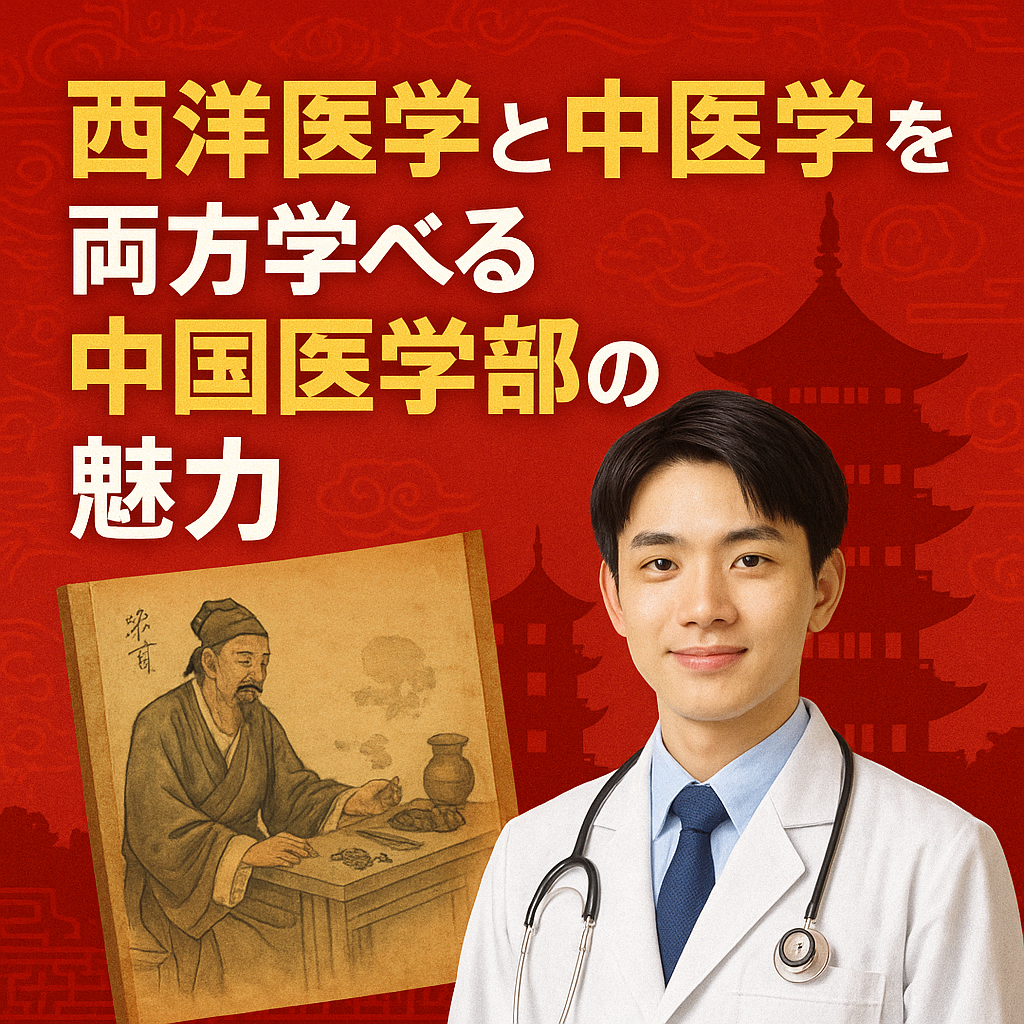
![認知症の診断と管理:プライマリケアから専門治療まで[2025年最新版]](https://med-pro.jp/media.dr/wp-content/uploads/2025/08/Gemini_Generated_Image_3ykf743ykf743ykf.png)