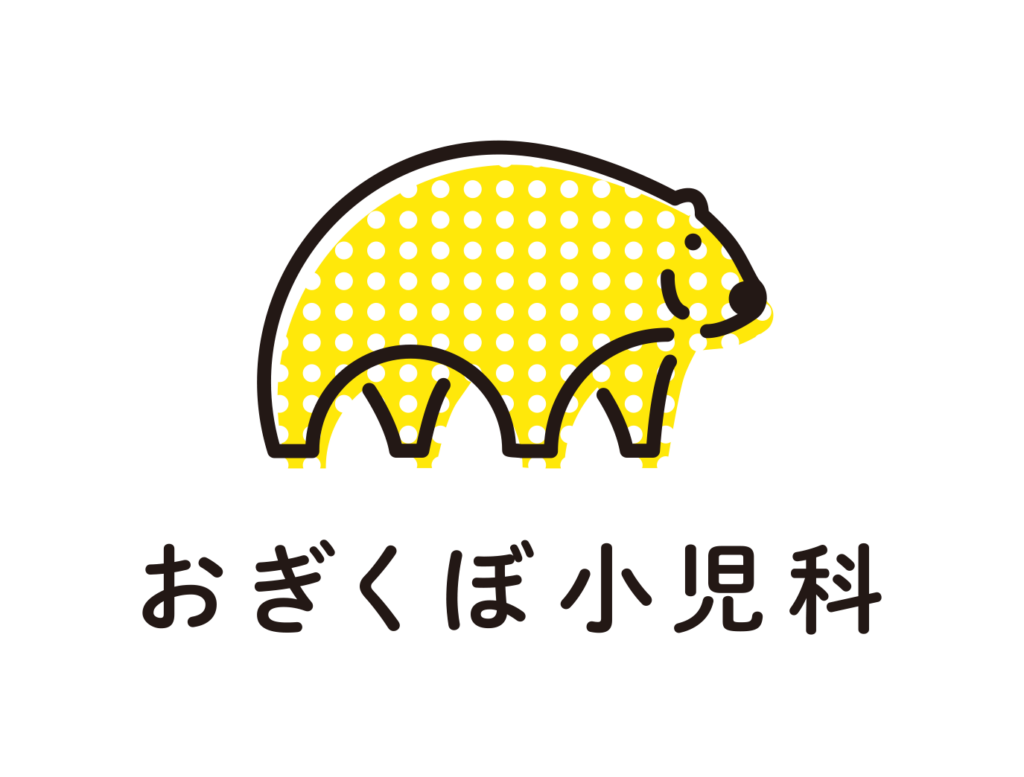専門医制度の発足以来、医師にとって専門医資格の必要性は常に議論の的となってきました。では、現代医療の視点から改めて「専門医は必要か?」を掘り下げてみましょう。
医師から見た専門医
医師の視点から見ると、専門医資格は「プロフェッショナルの証」として認識されています。しかし、資格を取得しない、あるいは維持しないケースも一定数存在します。その背景には以下のような理由があります。
- 専門医受験資格がない
研修プログラム未修了、転科、留学、研究専念などにより、受験資格が得られない場合があります。例えば、救急医として数年間勤務した後に研究職に移り、資格要件を満たせなかったケースが該当します。
<具体例>
外科医を目指していたDr. Aは、家庭の事情で急遽留学を中断し国内勤務に切り替えましたが、資格要件に必要な症例数に到達できず、受験資格を取得できませんでした。 - 専門医試験に合格できない
一部の診療科では試験難度が高く、合格率も低い傾向にあります。過酷な勤務環境の中で試験準備が困難になることも要因です。
<具体例>
Dr. Bは脳神経外科医として働きながら試験に臨みましたが、週80時間勤務のため学習時間を確保できず、3度目の受験でようやく合格しました。 - 専門医不要論
「経験があれば資格は不要」という考えの医師も存在します。患者に実力を評価してもらえれば資格は不要との立場ですが、他の医療従事者や医療機関から疑問視されることもあります。
<具体例>
開業医のDr. Cは、地域に根差した診療を続けることで、資格を持たなくても患者数が安定すると考えたため、あえて専門医を取得しませんでした。 - 更新できなかった
行政機関勤務や海外留学などで資格維持に必要な実績を積めず、更新できないケースもあります。
<具体例>
厚生労働省に出向していたDr. Dは、臨床業務から離れていたため専門医資格を更新できませんでした。
社会から見た専門医
社会的視点からは、専門医資格が医療の質と信頼性を担保する要素として認識されています。
- 信頼の証
患者にとって「専門医資格」は安心材料です。医療機関のウェブサイトで「〇〇専門医」と記載されることで、信頼感が高まります。
<具体例>
地域医療を担うクリニックが「小児科専門医在籍」とPRしたところ、口コミ評価が向上し、患者数が増加しました。 - キャリアの選択肢拡大
国内外の医療機関では専門医資格が採用の前提条件になることが増えています。海外留学や医療機関のポジション獲得にも有利に働きます。
<具体例>
Dr. Eは、消化器内科の専門医資格を取得後、オーストラリアの病院での就職に成功しました。 - 経済的インセンティブ
精神保健指定医など、資格取得により診療報酬が加算されるケースもあります。将来的には他の診療科でも同様の動きが見込まれています。
<具体例>
在宅医療クリニックで働くDr. Fは、緩和ケア専門医資格を取得し、診療報酬の加算により収入が20%増加しました。
専門医資格を取るべきか? 判断基準4つ
結局のところ、人によって答えは違うとしか言いようがありません。
しかしながら普通に臨床医を続けていく医師が、あえて専門医を取らない理由はなさそうです。しかし専門医を取るためには、それなりの時間が必要となります。何か他にやりたいことがあるのであれば、それを差し置いてまで取得すべきかは議論が分かれるでしょう。
あるDrの選択 〜多様なキャリアへの道〜
【背景】
地方の基幹病院で初期研修を終えた30歳のDr. Y。消化器内科を志望し、専門医取得を目指していたが、医療経営への関心が高まり、MBA取得のためにアメリカへ留学。
【選択】
留学後、大学病院に復職する選択肢もあったが、医療コンサルタントとして新たなキャリアを歩むことを選択。専門医資格は取得せず、経営視点で医療の質向上に取り組む道を選んだ。
【結果】
専門医資格がないために臨床復帰が制限されるリスクはあるものの、コンサルタントとして病院経営に貢献。医療経営と臨床現場の架け橋として活躍中。
【具体的な教訓】
専門医資格がなくてもキャリアは築けるが、臨床医としての選択肢が減る可能性があるため、将来的な計画を見据えて判断する必要がある。
結論:専門医資格は「目的」と「手段」を見極めて選択すべき
専門医資格取得は、キャリア形成や信頼性向上の強力な手段です。しかし、そのための年月は決して短くはありません。また必要性は個々の目標や状況によって異なります。「何のために専門医資格を取得するのか?」を問い直し、キャリア戦略の一環として判断することが求められます。
更新日:2025年2月14日
公開日:2023年6月13日
著者:鎌形博展
医師、株式会社EN 代表取締役、医療法人社団季邦会 理事長、東京医科大学病院 非常勤医師

東京都出身。埼玉県育ち。
明治薬科薬学部を卒業後、中外製薬会社でMRとなるも、友人の死をきっかけに脱サラして、北里大学医学部へ編入する。
卒業後は東京医科大学病院救命救急センターにて救急医として従事。2017年には慶應義塾大学大学院にて医療政策を学び、MBAを取得。東北大学発医療AIベンチャー、東京大学発ベンチャーを起業した他、医療機器開発や事業開発のコンサルティングも経験。2019年、うちだ内科医院を継承開業。以降、2020年に医療法人季邦会(美谷島内科呼吸器科医院)を継承し、2021年には街のクリニック 日野・八王子を新規開業。2023年には株式会社EN創業。国際緊急援助隊隊員・東京DMAT隊員・社会医学系専門医。趣味はBBQ。43歳で剣道・フェンシングを再開